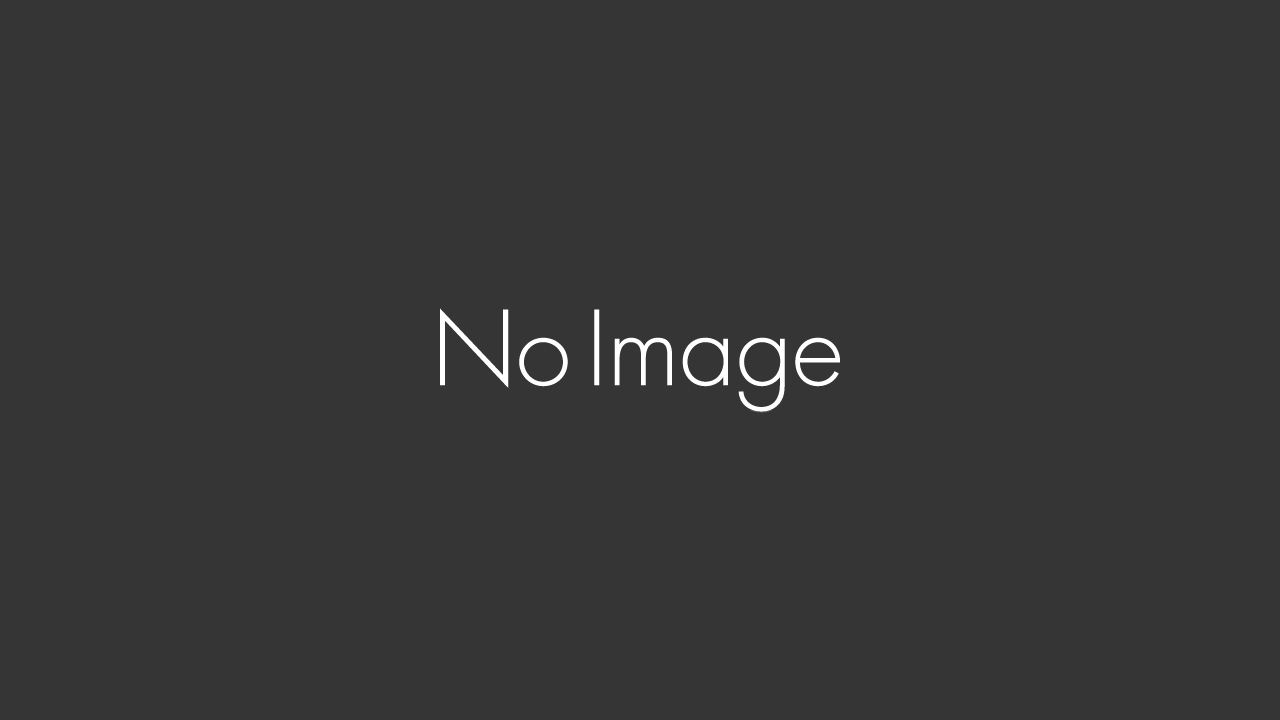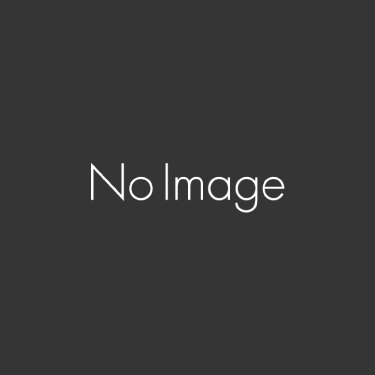日本航空123便の機長高濱雅己さん(当時49歳)の長女高濱洋子さん(48)が、父と同じ日本航空(JAL)で、客室乗務員の職に就いているのをご存じだろうか?
1985年8月12日。整備不良が原因でコントロールを失い、524人を乗せて御巣鷹の尾根に墜落した日本航空123便。
死者520人を出す単独機としては史上最悪の航空事故を起こした機体の機長は、墜落の寸前まで必死に乗客とその家族の為に戦った。
遺体の損傷は想像を絶するもので、結局5本の歯しか見つからなかった。
当時娘の洋子さんは高校3年生。
父を亡くした遺族でありながら、長らく機体を墜落させた戦犯の家族として、世間からの批判にさらされた。
複雑な思いで暮らしてきた30年がそこにあった。
自分自身も遺族である一方、“墜落したジャンボ機の機長の娘”という立場。事故当時、洋子さんにとって苦悩の日々が続いた。
高濱洋子さん「『519人を殺しておいて、のうのうと生きているな』とか、たくさん電話がかかってきましたので。
その度に母は、見知らぬ嫌がらせの電話にもきちんと応対し、『申し訳ございません』『申し訳ございません』、ただそれだけ何回も繰り返しておりました」
“父を探したい”、だが、昼間の遺体安置所には、多くの遺族がいた。そのため、ひと気がなくなる夜を待ってから父を探し歩いたという。
「父は機長だったので、ご遺族の方に対して私たちも遺族ですということは思ってはいません」
事故から15年が経ち、ボイスレコーダが公になった。
そこには最後まで乗客の為に必死に戦う操縦士達のやり取りが残されていた。
事故原因が機体の整備不良にあることも判明し、家族を取り巻く環境に変化が訪れた。
「父は本当に最後まであきらめず、最後の一瞬まであきらめず、頑張ったんですが、本当に無念であっただろう。最後まで父は頑張ったんだなと、誇りに思わなければいけない、そう思いました」
事故から3年後。そんな彼女が選んだ仕事は、父と同じ「空の仕事」だった。現在もJALの客室乗務員として、第一線で活躍している。
洋子さんには、初めてのフライトから持ち続けているものがある。
「唯一、コックピットの中にいる父ってこの写真しかないんですよね。なので、こんなボロボロになってしまったんですが」
所々がすり切れた写真。それは、父がコックピットで写る唯一の写真だった。
「JALの飛行機を守ってくれている、そういう思いから持っております」
飛行機の着陸前、洋子さんはいつも左胸に手を当てます。ポケットに入っているのは、父がつけていた4本線の機長の印。
「これを持っていることで、父が必ず守ってくれるだろうと」
父の思いを引き継ぎたかった。
「父の代わりに“空の安全を守っていきたい”。そういう思いでCA(客室乗務員)になりました」
空のプロとして非常に責任感の強かった父。常日頃から「理由はどうであれ、事故が起きたら全責任はキャプテンにある」と話していたそうだ。
「父の責任というのについては変わりなく、ご遺族の悲しみは消えることがないので、それはずっと私たちが背負っていかなければならない」
彼女にとって8月12日とは?
「父が残してくれたボイスレコーダーを聞き、新たに、また安全を守っていかなければという、再認識する、そういう一日かなと思います」
父に伝えたい言葉は?
「(事故から)安全を守ってきましたと父に報告したい。安心して空でゆっくりしてほしい」
間も無く亡くなった父と同じ年を迎えようとしている。
123便のパイロットの娘として、また父親を亡くした遺族として・・・
誰よりも辛い立場のはずなのに、決して逃げることなく現実に立ち向かう彼女の強さに、大きな感動を覚えた。
あれから今日で30年の年月が流れた。
30年経っても娘を失った悲しみは変わらない・・・
事故で娘を亡くした女性が、取材陣に向かってそう呟く。
もう30年なのか、はたまたまだ30年なのかは分からない。
しかし事故から30年経った今でも、遺族の悲しみは癒えることはない。
彼らは大切な人の前に引かれた「命の境界線」の意味を必死に追い求め、理不尽な神仏の気まぐれを嘆き、何もしてやれなかった自分自身への責めを繰り返すことだろう。
この世の生者必滅の習いとは知りつつも、時としてその残酷さには「何が神仏の加護だ」と、天に唾したくもなるものだ。
だが、悲しいかな我々は無力だ。
洋子さんが語るように、二度とこの様な悲劇が繰り返されぬよう、自分に出来る最善を尽くしながら、神仏の気まぐれにじっと身を任す他無い。
そんなことを考えさせられる。
私のとって8月12日とはそういう日だ・・・
※この記事は【丸腰の侍-世界をやんわり斬る】で書いた記事を転写しています。